この仕事向いてないなあ…
そう思ったことはないですか?
向いてない仕事はストレス一直線です。
では、あなたに向いてる仕事は何ですか?
それはそれで答えるのが難しかったりしませんか?
向いてる仕事を本人が正しく把握できていないのは珍しいことではありません。
仮に答えられたとしても、向いていると思い込んでるだけの可能性もあります。
自分の得意不得意を知るためには自己分析が効果的ですが、やり方がわからない、めんどくさいと思われがちです。
自己分析はコツさえわかれば難しいものではありません。
この記事では誰でもできる自己分析のコツとその方法についてをわかりやすく紹介します。
自己分析の重要性
自己分析をするタイミングといえば就活時をイメージするかもしれません。
もちろん就活時も大事ですが、社会人こそ自己分析が重要です。
自己分析は部署異動などの社内キャリアを考えるときだけでなく、転職時にも自分にとっての最適解を導いてくれるツールです。
これは私の経験談ですが、営業職から企画職への転向を希望して異動をしたことがあります。
営業経験があれば企画職もできるだろうと安易に考えていたのですが、私には企画をするためのスキルがありませんでした。
営業職は商品に関する情報やマニュアル化されたセールストークが設けられているので、その通りに実践すれば程度の差はあれ誰でも一定の成果をあげることができます。
しかし、企画という業務は形が何もなく、前例に捉われずに新しい取り組みをしていくことが求められます。
求められるスキルに明確な違いがあったことで、自分が得意なことは何か、できること、好きなことは何なのかを考えるようになりました。
自己分析で理解すべきこと

自己分析が重要な理由は自分の得意なことや好きなことを明確にすることですが、それだけではありません。
自己分析で最も大事なことは、苦手なことや嫌いなことを認識し、それを徹底して回避することです。
苦手なことを克服する努力をしても、苦手を好きになることはできません。
たとえば生理的に嫌いな人を好きになれと言われたらどうでしょうか。
好きになろうと努力したところで無理なものは無理ではないでしょうか?
私は絶対に無理です。
前より苦ではなくなった、マシになったと思えるかもしれませんが、できないことはできない、無理なものは無理なことがあります。
では、自分の好きなことや得意なことならどうでしょうか?
嫌いなことをしている時は時間が経つのが遅く感じる一方で、楽しいことや好きなことをしている時は時間の進みが早く感じると思います。
また、好きなことであれば何でそんなこと知ってるの?とまわりから思われるような細かなことまで覚えていたりすることはありませんか?
自分の好きなこと、得意なことに携わることができれば、早く深く理解して習熟度を高めることができ、それがあなたの強みになります。
時間は有限です。
無駄な努力をしたり効率の悪いことに時間を使うより、自分の得意なことにリソースを集中させることが大事です。
好きなこと、得意なことであればストレスもありません。
苦手を克服する努力と得意を伸ばす努力、同じ時間を使うなら得意なことに使いたいですよね。
自己分析で自分の苦手を可視化することで、将来後悔することのないキャリア形成ができます。
すぐにできる!自分の適性がわかる自己分析①
自己分析のやり方がよくわからないと感じる人は多いはず。
いざやってみても自分の考えが整理できない、言葉で表現できないなど、うまくいかないこともあると思います。
そこで、自分の仕事の適性がわかる簡単な自己分析の手法を紹介します。
仕事の適性は主に以下の3つに分類されます。
- 0から1を生み出す人
- 1を5や10に拡大する人
- 10を維持しながら11、12、13・・・と安定稼働させる人
0から1を生み出すタイプは、アイデア豊富にまわりを巻き込みながら前に突き進んで行くことができる人です。
このタイプは事業の立ち上げやビジョンの策定など、全体の方針方策を決めることを得意としますが、実務が雑であるなど、ルールや決まりを逸脱することを悪いと思わないような側面を持っています。
1を5や10に拡大するタイプは、試作品を改善改良して業務を軌道に乗せていく人です。
運用方法を確立して浸透させたり、部門間の調整を担ったりするなど、経験豊富かつコミュニケーション能力に長けている人はこのタイプに当てはまります。
10を維持・安定稼働させる人は、成長が止まった後にそれを維持継続させる人です。
マニュアル通りに業務をこなしたり、下準備や保守対応をしたりなど、会社員や公務員に最も多いタイプです。
あなたはどのタイプに当てはまりますか?
すぐにできる!自分の適性がわかる自己分析②
もうひとつ自己分析の手法を紹介します。
小学校の夏休みの宿題にどう向き合うかであなたの適性がわかります。
あなたは小学生の頃、夏休みの宿題にどう向き合っていましたか?
最も近いものを以下から選んでください。
- 早めに終わらせる、もしくは毎日コツコツやる
- 自由工作、自由研究にこだわる
- 最終日ギリギリにまとめて片づける
早めに終わらせる、毎日コツコツやるタイプの人は計画性のある人です。
スケジュールが定められている業務、ルーティン業務などに強みを発揮します。
自由工作などにこだわるタイプは、人によっては無駄なことに時間をかけていると思われかねません。
しかし、驚異的な集中力を発揮できる強みがあるため、プログラマーや研究職などのトライ&エラーを求められる業務に力を発揮します。
最終日ギリギリに片づけるタイプは、突発的なことに対処する能力を備えています。
営業などの対人交渉が向いている一方で、ルーティン化された業務は苦手です。
タイプ別で見る向いてる仕事・向いてない仕事
紹介した2つの自己分析、あなたはどのタイプに当てはまりましたか?
どのタイプにも強みと弱みがあるため、自分のタイプを把握することが重要です。
自分の当てはまるタイプを知ることでキャリアの方向性は自ずと見えてきます。
向いてる仕事、向いてない仕事の例をタイプ別に紹介します。
仕事には大きく分けて上流工程と下流工程があります。
上流工程とは裁量権を持って新しく仕事を作り上げていくポジションです。
新規事業や事業開発などの職種がこれに該当します。
先に紹介した0を1にするタイプだったり、夏休みの自由工作にこだわるタイプが向いています。
また、1を伸ばすタイプも上流工程です。
企画や戦略、推進、人事部門などがこのタイプに該当します。
次に下流工程ですが、これは上流で決まった方針をもとに実行する部隊です。
定型業務を行ったり、課題をコツコツこなしたり、仕事の裁量権は少ないが役割が明確であることを望むタイプが向いています。
経理部門や管理部門、IT保守などが下流工程に該当します。
先に紹介したタイプで下流工程に該当するのは、10を安定稼働させる人や、夏休みの宿題をコツコツ終わらせる人です。
このように自分の適性を把握することができれば、目指すべき仕事、学ぶべき分野が明確になります。
自分の適性を把握することは、部署異動だけでなく転職をする時など、キャリア選択の様々な場面で役立ちます。
選択肢は多く持つこと

自分のタイプを見極め、苦手なことや嫌いなことは割り切って『やらない』と決めることは、限られた時間を最大限活用するためには正しい戦略です。
しかし、視野を狭めすぎるのは注意が必要です。
会社員はまさにそうですが、自分のやりたい仕事があっても配属される部署によってはやりたい仕事ができないこともあります。
視野を狭めすぎていると、「これは私がやりたい仕事じゃない」というジャンルが増え、働くことそのもののモチベーションを保つことができなくなります。
異動にしろ転職にしろ、必ずしも希望どおりに事が運ぶわけではないので、関心の領域は幅広く、選択肢を複数持っておくことが大切です。
例えば簿記が好きで経理部で働きたいと考えている場合、選択肢は経理部だけではありません。
簿記は予算管理や経営企画部門など、様々な部署で活用できるスキルです。
また、法律が好きで法務部で働きたいという場合も選択肢はひとつではありません。
会社法という観点でいえば、取締役会を運営する経営部門や総務部門も候補になり得ます。
苦手な事や嫌いなことは避けるべきなのは絶対ですが、好きや得意の領域を点ではなく面で捉えて考えることが大事です。
自己分析は難しくない
自己分析を正しく行うことで、あなたの価値観と仕事のミスマッチを防ぐことができます。
苦手なことや嫌いなことはストレスの原因です。
自己分析でそれらを避けることができれば幸福度の向上にもつながります。
自己分析は面倒で難しいものと思われがちですが、慣れてさえしまえばそんなことはありません。
今回の記事を参考にぜひ自己分析を行ってみてください。
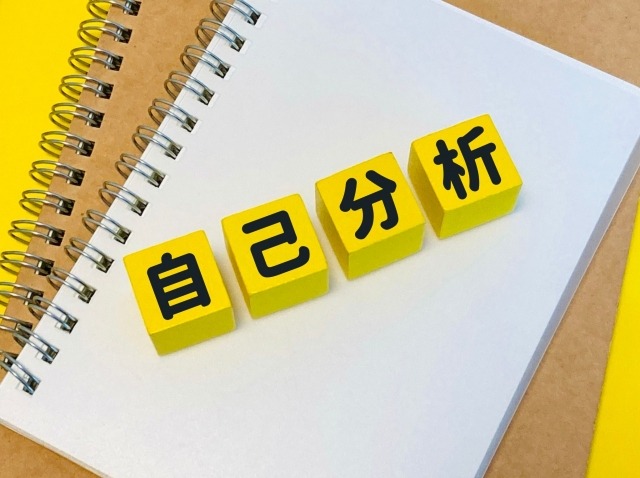


コメント