業務が特定の個人に依存することは会社にとってリスクです。
担当者が休職・退職した場合、急な欠勤時など、業務の継続が困難になります。
一方、一従業員目線で見た場合、人手不足で仕方なくという場合を除き、属人化をリスクではないと考える人もいます。
既得権益の維持、存在価値の誇示など、仕事を独占することで得られるメリットがあるからです。
しかし、果たして本当にそうでしょうか。
私自身仕事を属人化していた時期があり、その恩恵を享受できた時期があります。
一方で属人化による弊害も数多く経験してきました。
この記事では私自身の体験を踏まえ、会社目線ではなく会社に所属する一従業員にとって、仕事を属人化することは損なのか得なのかを解説します。
属人化で困っている人はもちろん、意図的に属人化をしている人にとって気付きのある内容です。
属人化は損か得か
従業員目線で見た場合の属人化は得するのか、それとも損するのか。
私の経験上、ある一定の時期までは得をすることのほうが多いです。
ただし、私の知る限り、私を含む継続的に属人化を続けている人は、最終的にもれなく全員損をしています。
これには明確な理由があります。
理由は後ほど詳しく解説しますが、まずは仕事を属人化することで起こりうる良い面と悪い面をそれぞれ整理していきます。
属人化のメリット
業務を属人化することのメリットは『既得権益を得ることで存在価値をアピールし、自身にとって都合のいいキャリア形成を築ける』ことです。
もしもあなただけしか知らない業務があった場合、他の人はあなたに頼らざるをえません。
「〇〇さんがいないと困る」「〇〇さんがいないと業務が進まない」という環境を作り出すことで職場内で発言力が増し、周囲に強い影響力を及ぼすことができます。
属人化している業務が重要なものであるほど権威は強くなり、居心地のいい環境を醸成しやすくなります。
また、いなくなると業務に支障がでることから異動の候補になりにくく、その職場を気に入っていて異動したくない場合に有効です。
このように知識やノウハウを独占し、自分にとって都合のいいポジションを確保できることが属人化の大きなメリットです。
本人にとっては業務を自分に属人化させて誰にも引継ぎをしなければ既得権益が守られるため、わざと自分の業務を複雑にしたり、業務改善や新システムの導入に消極的な姿勢を見せたりします。
属人化のデメリット
業務の属人化は会社にとってはリスクになる反面、従業員目線ではメリットがあると述べました。
ただし、従業員目線でもデメリットはあります。
それは仕事が減らないことです。
属人化している業務が重要であればあるほど、残業時間が増えたり休暇を取得しづらいといった弊害が生じます。
また、仮に休みが取れても上司や同僚から緊急の連絡が入る可能性も否定できません。
既得権益を守るためにはプライベートを諦めて仕事優先の生活を覚悟する必要があります。
属人化が損する理由
先に述べた通り、業務の属人化をしていると最終的には損をします。
メリットもあるのになぜ損をするのか、その理由は仕事の評価が下がるからです。
会社員は日々の働きに応じて上司から評価をされ、その結果に基づいて昇給や昇格の是非が判断されます。
会社では通常業務、ルーティン業務は日々改善を図ることで仕組み化し、空いた時間で新しい取り組みを進めるというサイクルが求められます。
しかし、属人化して仕組みを作らず、仕事量が減らない状態が続くと、業務効率が悪いと判断されかねません。
また、新たな取り組みに時間を割くこともできないため、生産性が低いとみなされてしまいます。
このような状態を続けていれば当然評価はされず、昇給や昇格の機会を失いかねません。
これだけならまだ傷は浅いかもしれませんが、慢性的に悪い評価が続いてしまうと「あいつ一人に任せておけない」とまわりから判断されてしまい、強制的に仕事を外されたり配置換えをされたりするなど、これまで頑なに守ってきた既得権益をあっという間に失ってしまうという最悪の結果につながりかねません。
会社という組織に属する以上、従業員個人での抵抗は限界があります。
既得権益を守ろうとしすぎると手痛いしっぺ返しをくらう可能性があるので注意が必要です。
属人化の末路

業務を属人化する人は一定の時期まで恩恵を受けるが、最終的に損をすると先に述べました。
どのようなキャリアを歩むことになるのか、時系列で解説すると以下のようになります。
- 属人化により『自分だけが知っている』業務の領域ができる
- まわりから頼られる機会が増え、自分は仕事ができる人と勘違いする
- 属人化した業務とその周辺業務に対する発言権が増し、仕事の裁量権を得たと勘違いする
- 業務が属人化していることに危機意識を感じた上司や所属長から現行業務の改善を求められる
- 裁量権などの既得権益を手放したくない気持ちが勝って改善を実施しない
- 属人的な業務が減らないため、慢性的に仕事が終わらず残業の機会が増える
- 生産性の低さ、業務効率の悪さを理由に評価が下がり、昇進の機会を逃す
- 改善が図られないまま、人事異動により業務を強制的に引き剥がされる
- 独自のルールなど、無駄に複雑化された業務により引継ぎがままならない
- 属人的な業務に慣れすぎた結果、新部署で可視化・仕組み化された業務フローになじめない
- 業務効率が悪いと見做され、また評価が下がる
業務の属人化は頼られる(頼らざるを得ない)機会が多いため気付きにくいのですが、そのままのスタイルで仕事を続けていると自分が損することになるため早めの対策が大事です。
意図的に業務を属人化している人もそうでない人も、自身が携わる業務内容を踏まえて立ち居振る舞いを見直す必要があります。
属人化をやめる方法
組織にとって業務の属人化は持続的な経営を行ううえで大きなリスクです。
そのため、属人化の解消、業務の仕組み化は組織にとって優先度の高いタスクです。
つまり、属人化を解消する取り組みは組織への貢献を意味し、自分の評価を上げるチャンスになります。
業務の属人化を解消する方法は、仕事に対する執着心やこだわりをなくすことです。
業務の属人化をする人の特徴は、その仕事が好きで誇りを持っている人、もしくは自己肯定感が低く居場所を失うことに不安を感じている人です。
好きだからこそこだわりが強くなったり、不安だからこそ執着心が生まれてしまいます。
これを解消するためには所詮は仕事だということ、そして組織において人一人の力はたかが知れているということを理解することです。
そのうえで新しいことを始めればこだわりも不安も少しずつ和らいでいきます。
割り切ることが属人化解消の一歩です。
属人化を避けることはできない
誰しもが業務の全てを把握することはできないため、属人化の発生はどうしても起こりうるものです。
避けてとおることはできないため、属人化が発生することを前提に、いかに早くその状態を解消するかが重要です。
属人化の期間が長ければ長いほどキャリアは傷ついていきます。
『属人化は明確に損である』ということを踏まえ、業務の可視化・仕組み化を進めることを強く推奨します。
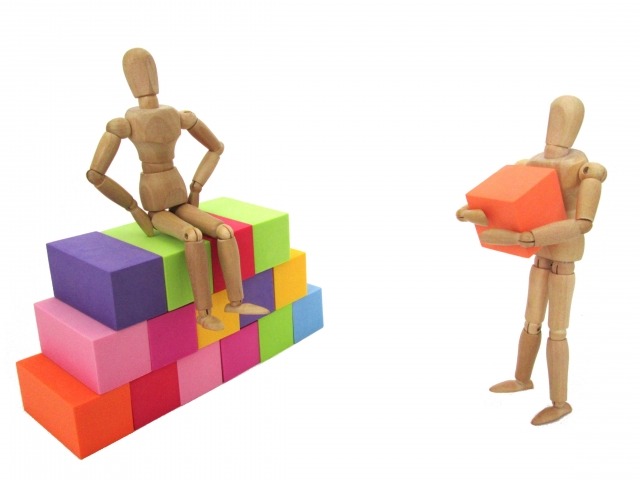


コメント